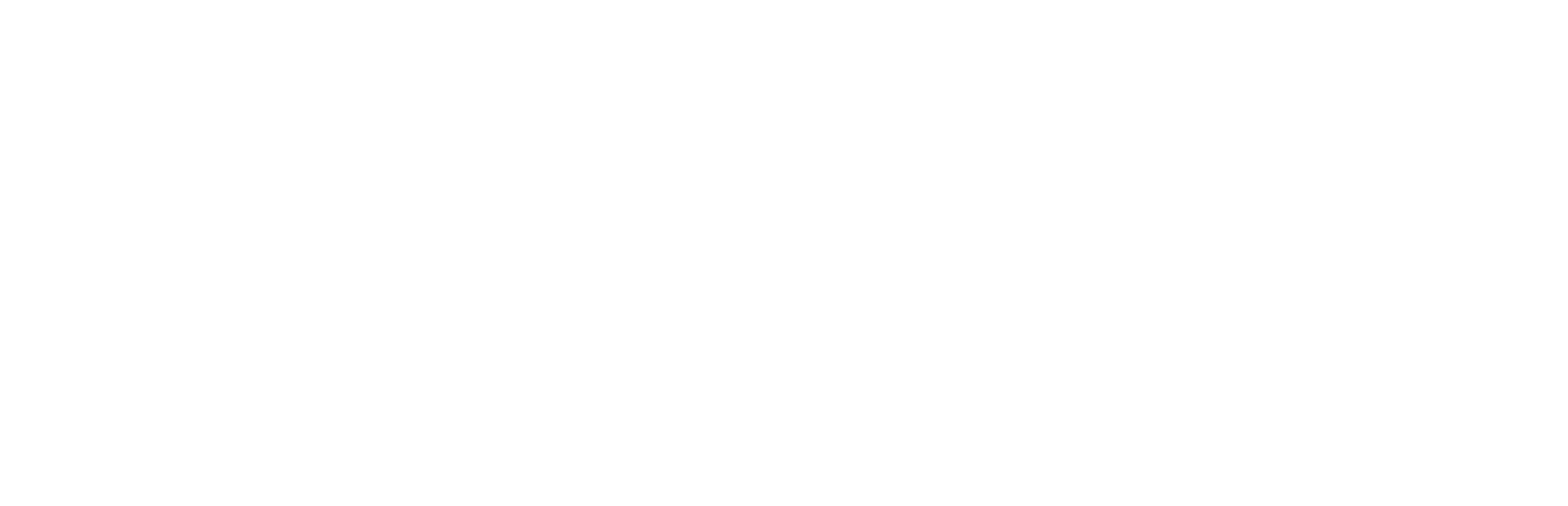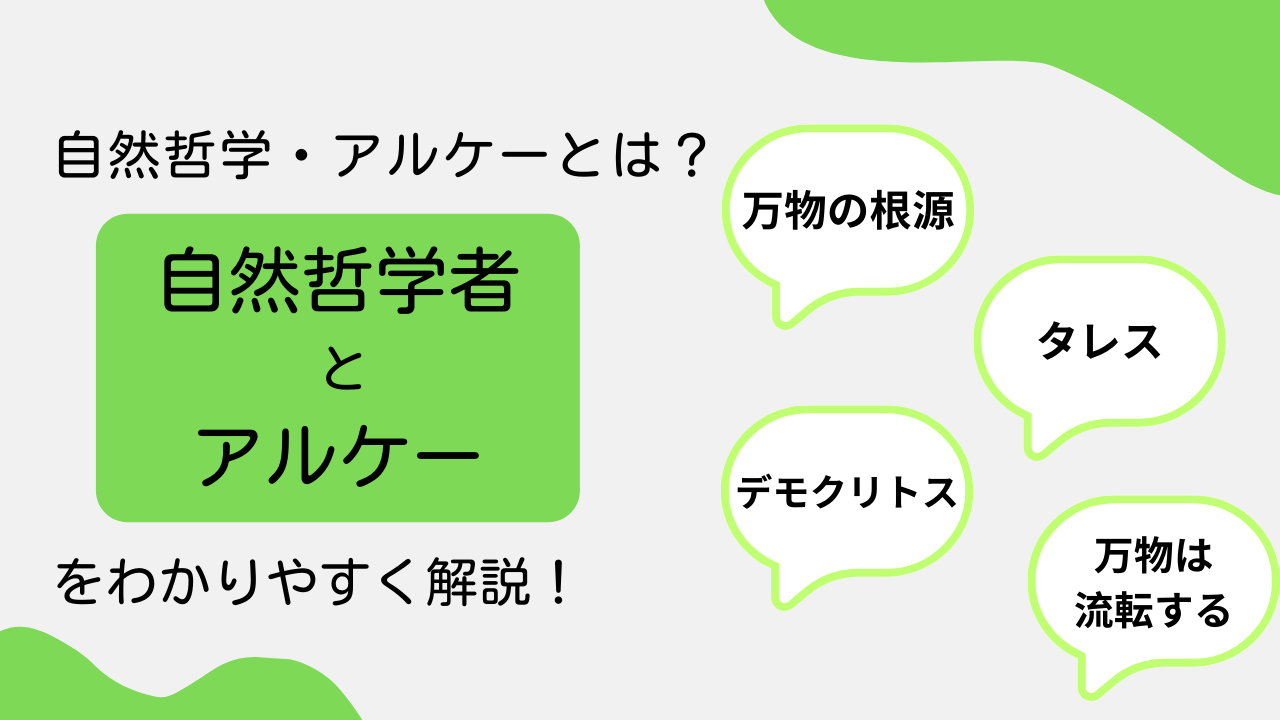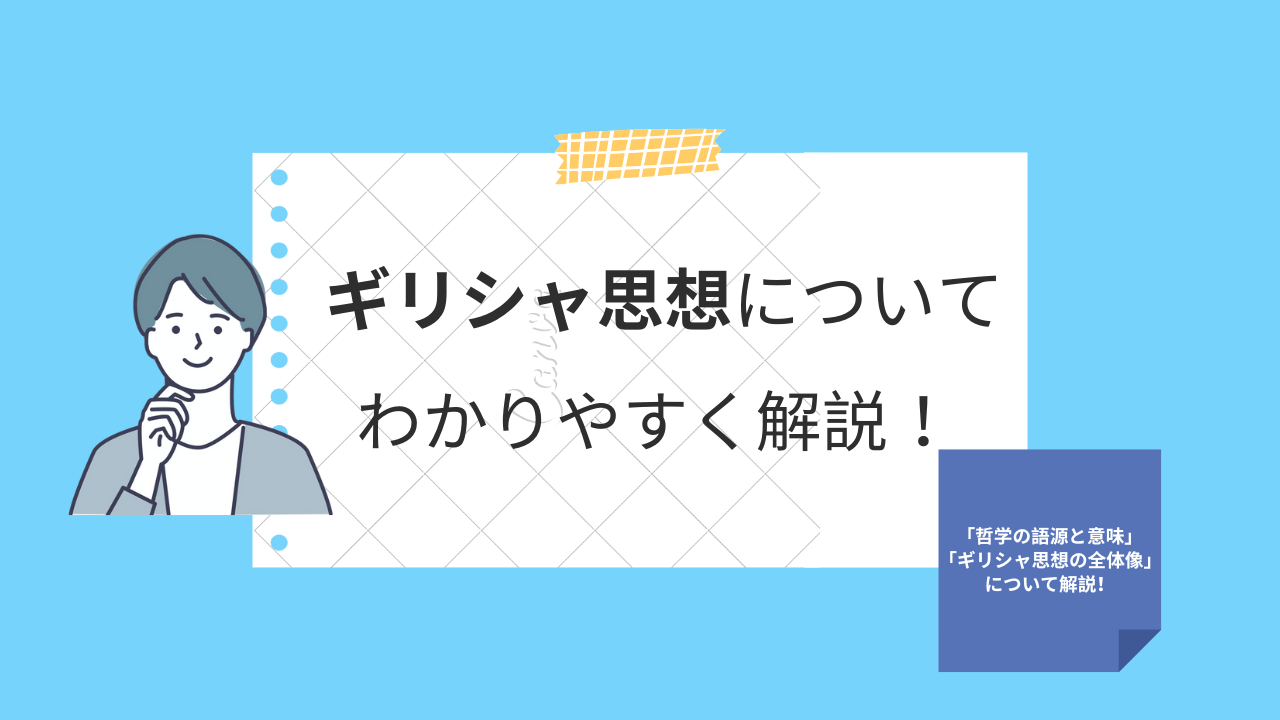こんにちは、りゅう先生です!
今回はギリシャ思想で重要な「自然哲学」と「万物の根源(アルケー)」について解説していきます。

「自然哲学」って?自然を哲学するってどういうことだ?

万物の根源と何か関わりがあるんじゃないかな?
自然哲学とは、「自然」そのものを理性(ロゴス)で理解しようとする哲学です。
自然哲学では特に、「世界は何からできているのか?」という万物の根源(アルケー)が探究されました。
この記事では5人の自然哲学者と対応するアルケーについて解説しています。
それぞれわかりやすく、かみ砕いて説明しているので、ぜひ最後まで読んで理解を深めてください!

それぞれの自然哲学者の思想やアルケーを理解しよう!
- 「自然哲学」と「万物の根源(アルケー)」の意味
- 自然哲学者に対応するアルケー
- 自然哲学者とアルケーの覚え方
自然哲学と万物の根源(アルケー)とは
自然哲学とは、「自然」そのものを理性(ロゴス)で理解しようとする哲学です。
例えば、「雷が発生するのは神様の怒り」と誰かに教えられたとしましょう。
しかし、自分で色々考えた結果、「雲の中にたまった電気が地面に向かって放電している」と気づいたとします。
これがまさに「理性」を使って世界を説明していることになります。
自然哲学では特に、「世界は何からできているのか?」という万物の根源(アルケー)が探究されました。

アルケーとは、すべてのものの「元になるもの」という風にとらえましょう!
ちなみに自然哲学が誕生する前は、神話を用いて自然や人間の出来事を説明していました。
神話的世界観から自然哲学が生まれた背景については倫理で学ぶギリシャ思想・哲学を始まりからわかりやすく簡単に解説!をご覧ください。
自然哲学者と万物の根源(アルケー)の一覧
ここからは、自然哲学者と万物の根源(アルケー)を確認しましょう。
テストにもよく出る重要な5人とアルケーを表にまとめましたので、確認してください。
| 人物 | アルケーととらえたもの |
|---|---|
| ① タレス | 水 |
| ② ピュタゴラス | 数 |
| ③ ヘラクレイトス | 火 |
| ④ デモクリトス | 原子(アトム) |
| ⑤ エンペドクレス | 火・空気・水・土(四元) |
| ⑥ アナクシメネス | 空気 |
太字の人物については、以下で詳しく解説しています。
それぞれの人物がどのようにアルケーをとらえていたのか、解説を読んでしっかりと理解しましょう。
① タレス:「水」
タレスはアルケーを「水」ととらえました。
生命に水が欠かせないことや、水が液体・固体・気体の3側面すベてに変化することから、水がアルケー(万物の根源)と考えました。

タレスは自然哲学の創始者で、「哲学の祖」とも呼ばれます!
② ピュタゴラス:「数」
ピュタゴラスはアルケーを「数」ととらえました。
彼は音楽や天体の運動が数学的な法則で説明できることに着目し、数こそが万物の根源だと考えました。
数学や音楽を手段としながら、魂の浄化(カタルシス)を目指し、のちにピュタゴラス教団を設立しています。

三平方の定理(ピュタゴラスの定例)を発見した人としても有名だよ!
③ ヘラクレイトス:「火」
ヘラクレイトスはアルケーを「火」ととらえました。
火は燃え続けることで形を変えながら存在し続けるため、彼はこれを「万物は流転する」という変化の象徴としました。
つまり、世界は「何かからできている」のではなく、「絶えず変化し続けている」と考えたのです。

ヘラクレイトスの考えを象徴する言葉として、「二度同じ川に入ることはできない」というものがあるよ。川に二度入っても、絶えず流れて変化している川は以前とは同じではないと捉えているんだね。
④ デモクリトス:「原子(アトム)」
デモクリトスはアルケーを「原子(アトム)」ととらえました。
原子は非常に小さく、それ以上分割できない粒子で、原子が組み合わさって世界を構成していると考えました。
目に見えないものにまで考察を広げた彼の思想は、後の科学にも影響を与えました。
自然哲学者とアルケーの覚え方
ここまで自然哲学者とアルケーを解説してきました。
たくさんの用語が出てきて、少し混乱していると思いますので、ここで覚え方の紹介をしたいと思います。
大前提として、倫理では用語の暗記よりも、理解の方が大事です。
とはいってもテストで点を取るために覚えなくてはならないこともあるので、用語を理解した上で、以下の覚え方も参考までに活用してもらえたらと思います。
| 覚え方 | 省略前 |
|---|---|
| タレ水 | タレス:「水」 |
| ピュタゴラ数 | ピュタゴラス:「数」 |
| 火ラクレイトス | ヘラクレイトス:「火」 |
| アトムが原発のデモに参加 | デモクリトス:「原子(アトム)」 |
| 炎天下で空気薄い土曜は水・火に注意 | エンペドクレス:「火・空気・水・土(四元)」 |
| 穴閉めすぎで空気薄い | アナクシメネス:「空気」 |
繰り返し言葉にしてみてください。
10回ぐらい声に出してみると覚えられるかと思います!
演習問題にチャレンジ!
- Q古代ギリシャの自然哲学者が探求した、万物の根源を指す言葉は何?
- A
アルケー
- Q万物の根源を「水」と考え、自然哲学の始まりを築いた哲学者は誰?
- A
タレス
- Qピュタゴラスが主張した、宇宙の秩序を形作る根源的なものは何?
- A
数
- Q変化の象徴として「火」をアルケーと考えた哲学者は誰?
- A
ヘラクレイトス
- Q上記の人物が唱えた、世界は常に変化し続けるという思想を表す言葉は何?
- A
万物は流転する
- Q世界は「原子(アトム)」と空虚から成り立つと主張した哲学者は誰?
- A
デモクリトス
「自然哲学・万物の根源(アルケー)」のまとめ
この記事では「自然哲学・万物の根源(アルケー)」について解説しました。
最後に、テストにもよく出る「自然哲学者とアルケー」について、覚えた方も含めて表にまとめましたので、おさらいしてください。
| 人物 | アルケー | 覚え方 |
|---|---|---|
| ① タレス | 水 | タレ水 |
| ② ピュタゴラス | 数 | ピュタゴラ数 |
| ③ ヘラクレイトス | 火 | 火ラクレイトス |
| ④ デモクリトス | 原子(アトム) | アトムが原発のデモに参加 |
| ⑤ エンペドクレス | 火・空気・水・土(四元) | 炎天下で空気薄い土曜は水・火に注意 |
| ⑥ アナクシメネス | 空気 | 穴閉めすぎで空気薄い |
最後まで読んでくれてありがとうございました!